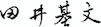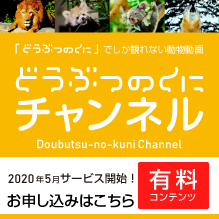『どうぶつのくに』をご愛読くださる皆様へ

『どうぶつのくに』をご愛読、また様々な形でご支援・ご尽力くださる皆様におかれましてはますますご健勝のことと存じます。
現在、新型コロナウイルスCOVID-19の影響を受け、多くの文化活動や経済活動が自粛を求められています。私たちの愛する動物園や水族館もその多くが休園・休館を余儀なくされていることもご存知の通りでしょう。実際ヨーロッパやアメリカでは早くも倒産・閉園を迎えた園館が少なくなく、飼育動物たちを殺処分せざるを得なかったり、それをまた他の動物の餌とせねばならなかったり・・・悲しい現実がすぐそこにあるのです。
ついては弊誌『どうぶつのくに』もこの世界的な情勢が落ち着くまでの間、一時的に印刷物としての本誌発行を見合わせる一方で、当面の間は公式サイト「どうぶつのくに.net」のコンテンツ増強に注力することと致しました。月刊印刷物としての本誌に負けないコンテンツを同サイトでご用意することで、読者の皆様にはしばしご自宅から動物たちの魅力をお楽しみいただけるようにと熟慮を重ねた結果です。なお大変勝手ながら、セキュリティ強化と運営上の観点からもこれを機に「どうぶつのくに.net」のご利用を会員制とさせていただくことと相成りました。
これまでになかった世界中の動物たちの動画コンテンツや、新たな連載コラム、また世界の動物園・水族館にまつわる情報発信なども当サイトで積極的におこなってまいります。
会員制に切り替わりますのは2020年5月18日を予定しておりますので、ご面倒ですがそれ以降に会員登録のお手続きをいただければ幸いです。
ウイルスのことは今回たしかにひとつの契機ではありますが、“大切な人やことを守り、そして強くしてゆく”というテーマについては常々小誌が課題としてきたことでもあります。『どうぶつのくに』をしなやかに進化させながら守れるように、精一杯努力してまいります。
ご不便をおかけする点については重ねてお詫びを申し上げるとともに、何卒ご理解とご協力のほど、こころよりおねがい申し上げます。
2020年 4月吉日
『どうぶつのくに』編集長 田井基文
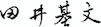
『どうぶつのくに』編集長 田井基文