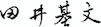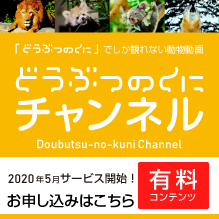澄んだ空に黒い噴煙を吹き上げる桜島。
冬は北西の風が強いため、水族館のある薩摩半島側には降灰が来ないので、内心若干の安心と、灰が降る大隅半島側の心配をしつつ、錦江湾に潜っていく。
湾内は豊富なプランクトンであまり透明度は高くはなく、例年よりも水温の下降が遅れておりまだまだ濁った水中ですが、例年この時期は水深が1mほどの浅い転石帯に目をやるとコノハミドリガイがあっちにもこっちにも・・・。
というのが普通でした。

*これは八代海のコノハミドリガイの群れですが、錦江湾内も同様の状況になります
コノハミドリガイは一年生の種と考えられ、毎年晩夏頃に小型の新規加入群が姿を現し、ハネモを食べて少しずつ成長し、2~3月頃には10㎝を超える最大体長に達します。

ハネモを食べるコノハミドリガイ

体長約12㎝のコノハミドリガイ
この後、ハネモの衰退とともに春から夏にかけて寿命を迎え、海から姿を消していきます。

餌不足で葉緑体が失われ体色が白くなってしまったコノハミドリガイ。このまま餌が足りない状況が続くと衰弱して死んでしまう。
このため、春から夏まではコノハミドリガイを発見しにくいのですが、秋からは新規加入群がたくさん見つかります。

新規加入のコノハミドリガイ。体長20㎜弱
特に水族館前のイルカ水路には毎年何百(いやもしかすると何千の年も)という個体数が出現します。
それくらいTHE普通種のコノハミドリガイですが、今年はいつもと違いました。
私は研究のために定期的にコノハミドリガイの採集を行っていますが、今年は9月頃に出現した多数の新規加入群を見つけ安心した後、11月にはほとんど見つけられなくなってしまいました。
一体何が起こったのでしょうか。
今年が例年と違うのは、夏の猛暑でしょう。
猛暑の影響で餌となるハネモ類の生育や付着状況が例年よりも悪い可能性があります。
その状況に多数のコノハミドリガイ幼生がやってくることで、ハネモの新芽を食べ尽くしてしまい、餌が無くなってしまったのかもしれません。
あるいは、生育し始めのコノハミドリガイ幼体があまりにも下がらない水温に耐え切れなくなったか・・・・(夏に着底するので考えにくいですが)
いずれにしても、海域によって状況は違うはずです。
同じ錦江湾でもやや深かったり水流が違ったりとする場所ではハネモが生き残っている可能性もあります。

ハネモ
そこで育つコノハミドリガイが産卵してくれればまたコノハミドリガイが戻ってくるでしょう。
今年は特に慎重にコノハミドリガイの動向を見守っていきたいと思います。